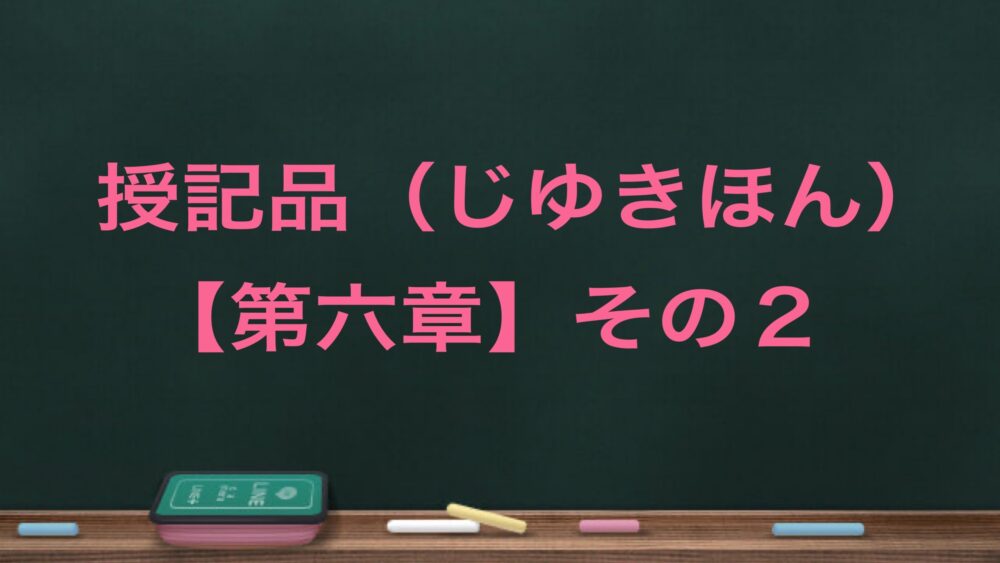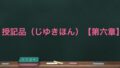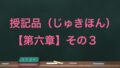法華経【第六章】授記品その2
四大声聞への授記
法華経と共に
さっそくですが、前回の続きをさせて頂きます。
「軌道が定まる」というお話がありましたが、これは「授記」という言葉の元意にも一致しています。
「記」という漢字は元来、ものごとを立て分け、筋道を立てて表すという意味です。
漢訳の「授記」は、鳩摩羅什が使い始めた訳語で、それ以前は「記別」「授決」などと言っていました。
記別の「別」も立て分けて区別するという意味ですし、受決の「決」は、はっきりと立て分けて取り決めることです。
「授記」のサンスクリットの原語は「ヴィヤーカラナ」と言います。
これには、「区別」「分析」「発展」などの意味があります。
仏典では、疑問に対して明確に答えること、という意味で用いられています。
要するに、授記の「記」というのは、明確に述べることです。
明確に述べることによって、成仏への軌道を最後まで間違いなく歩ませるのです。
信解とは、向上への志であることは、すでに確認しましたが、その志を生命の奥底に刻む力が、授記にはあるのでしょう。
元来、授記とは、明快な答えを述べ、人々の心の疑いを解決することだということです。
リーダーはつねに「明快」でなければならない。
あいまいは悪になる。
人々に不安をあたえるからです
「確信をあたえる」のが「授記」のポイントです。
経典で述べられている「授記」「記別」の大半は、死後どのようになるのかに関するものです。
死後や未来にどうなるかは、はっきりとは分からない。
だからこそ「明快に語る」必要があったのではないでしょうか
天台大師も、授記とは「言葉を用いて弁える」ことだ、と述べています。
仏が「記を授ける」(授記)のは、その人自身に、成仏できることを、はっきり弁えさせるためです。
自覚させ、確信させるのです。
授記品では、四人の声聞のうち、まず、迦葉に対して授記が行われます。
その光景を見て、目連ら三人が自分たちも授記を受けたいと釈尊に願い出ます。
釈尊は、須菩提、迦旃延、目連の順で授記を与えていきます。
目連ら三人が授記を願う場面では、大王膳の譬えが述べられています。大王膳=飢えた国から来た人が、突然大王から食膳に出されたとしても、心の中にはまだ疑いや恐れがあって、すぐには食べることができない。しかしもし王から「食べよ」とのお言葉を賜れば、その時になってはじめて安心して食べることができる。
この譬えの背景には、法を聞いてもすぐには受け入れられず、仏や王の確かな保証があってはじめて安心して信受できる、という意味合いが込められています。
すなわち、授記を願う心境は、飢えた国からやって来て「大王の膳」つまり最高級の料理を目の前にしているようなものだ、と。
食べたくて仕方がないけども、王の許しがなければ安心して食べられない。
同じように、「声聞も成仏できる」という一仏乗の教えを聞き、納得したけれども、仏から明確な授記を与えられなければ真の安心は得られないというのです。
ちなみに、三人の言葉の中で、釈尊が授記を与えることを「甘露を注ぐ」と譬えています。
「甘露」は不死を意味する梵語「アムリタ」の訳で、天界にある不老不死の妙薬のことです。
授記には、今世だけではなく、未来世にもおよぶ力があることが暗示されています。
生命の根底の不安を取り除き、絶対の安心をあたえる。
授記には、こういう効果がある
授記という仏の保証によって、生命の根底に未来への深い確信が得られたのです。
四大声聞が成仏するときの劫・国・名号を具体的にあげているのも、この確信を強めるためではないでしょうか。
「劫」すなわち成仏する時代の名前、「国」すなわち成仏する国土の名前、「名号」すなわち仏としての名前などが具体的に示されます。
四大声聞への授記で言えば、次のようになります。
1.迦葉は、大荘厳の時代に、光徳という国で、光明如来になる
2.須菩提は、有宝の時代に、宝生の国で、名相如来になる。
3.迦旃延に関しては、名号だけが示されているだけで、閻浮那提金光如来になる。
4.目連は、喜満の時代に、意楽の国で、多摩羅跋栴檀香如来になる。
釈尊は、弟子たちに威徳があるゆえに授記すると述べていますが、劫・国・名号には、弟子の長所・個性と何らかの関連があるように感じられます。
最初の迦葉は、光明、光徳と、光という言葉が用いられています。
「光明」という如来の名は、梵語では、栄光の輝きという意味あいがあります。
「光徳」という国の名は誉れある世界、栄光にあるれる世界という意味です。
「大荘厳」という劫の名も、偉大なる輝かしい姿という意味です。
迦葉は、名門の家柄でしたが、釈尊よりも早い時期に出家し、正しい法を求めて遍歴していました。
やがて、釈尊に巡り会い、ひとめ見るなり弟子となったと伝えられています。
釈尊が自分より粗末な衣服を着ているので、自分の衣服を釈尊の使い古しと交換し、それをずっと身につけて、清貧の修行である頭陀行に徹したとされます
弟子たちの中には、粗末な衣服をまとった迦葉を疎んじた、心ない人々もいたようですが、釈尊は正反対でした。
迦葉を「修行者の先輩」と仰いで、自身と同じ高座に座らせ、「頭陀第一」と賞賛しています。頭陀=衣食住に対する欲望を払いのせること。
最も地味な修行に徹する迦葉を、釈尊は最も輝く人と見ていたわけです。
頭陀と言えば、薬草喩品(第五章)の後半、鳩摩羅什訳にはない部分にある譬えでは、雪山(ヒマラヤ山脈)の薬草で盲目を治した人が、さらに頭陀行で「千里眼の神通力」を得たとされています。
この譬えからも、頭陀行と光明との関連がうかがえます。
その頭陀行の功徳は、「法華経を信解する功徳」を譬えたものです。
その功徳とは、未来にわたる、心の光明を得ることです。
それが人間としての、最高の栄光でもある。
仏の智慧の光にも、人生の苦悩の闇を払いのける力がある。
この仏のイメージを迦葉の長所と重ねあわせて「光明如来」と名づけたのかもしれない。
大聖人も「今日蓮等の類い南無妙法蓮華経の光明を謗法の闇冥の中に指し出だす此れ即ち迦葉の光明如来なり」と仰せです。
謗法の闇を払いのける妙法流布こそ、最高の頭陀行なのです。
後の三人のお話は、次回に続きます。
ご視聴ありがとうございました😊
法華経【第六章】授記品その2