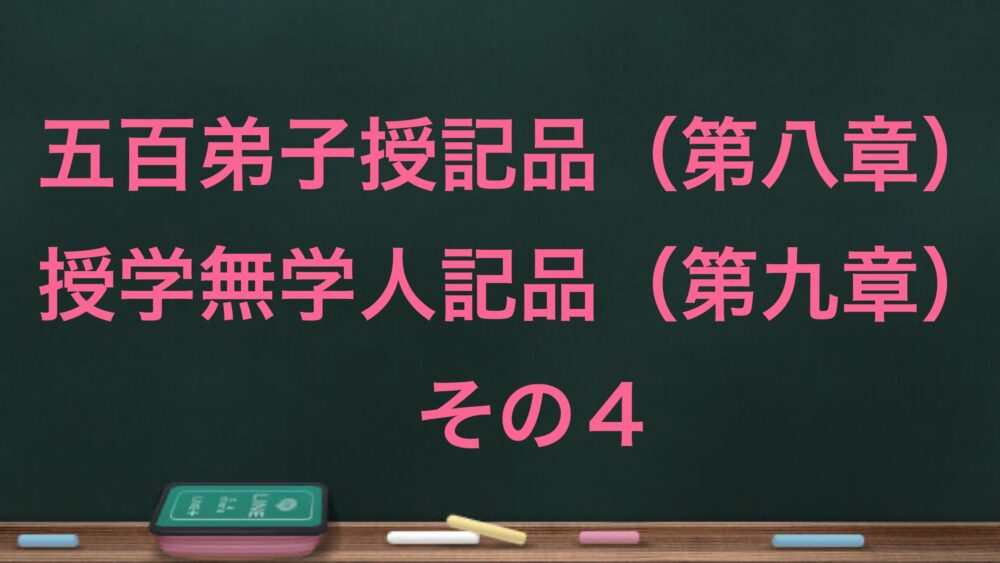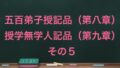【法華経】五百弟子授記品(第八章)授学無学人記品(第九章)4
「人の開会」と「法の開会」
法華経と共に
これまでに、学んで来たように、譬喩品(第三章)に始まって、舎利弗以下の声聞が次々と成仏の授記を受けますが、これは、「救われる人」から「救う人」への革命。つまり、声聞が菩薩になったということです。
方便品(第二章)には「但だ一乗の道を以て 諸の菩薩を教化して 声聞の弟子無し」とあります。
これは、方便品のところですでに確認した「人開会」です。
一乗の道(法華経)によって教化される衆生は、すべて菩薩であるというのです。
「開会」とは、別々のものと思われたものを、より高い次元からとらえて、統一することです。
開会を「法」で言えば、仏は、ただ一仏乗を説くだけで、三乗(声聞乗・菩薩乗)という別々の教えはないとする。
三乗を別々の教えと見るのは、教えを受けとる衆生の側であって、より高い仏の次元では、成仏へのただ一つの道、一仏乗を説いているだけであると統一するのです。
「人」で言えば、仏は、成仏をめざす菩薩を教化しているだけであって、教化する弟子に声聞や縁覚・菩薩の区別はないとします。
この「人開会」では、仏は、すべての衆生は生命の奥底に「成仏をめざす心」「仏の智慧を求める心」があると見ています。
その次元から、すべての衆生は菩薩であると統一するのです。
五百弟子品の冒頭で、富楼那は、三千塵点劫以来の釈尊との師弟の因縁を説いた化城喩品(第七章)の説法を聞いて、自身の「深心の本願」を自覚しています。
つまり、自分は、はるかな昔から成仏を願い、師である釈尊とともに菩薩の実践をしてきたのだ、と。
声聞である以前に、菩薩だった。それが本来の自分であるという自覚です。
この「深心」の次元で、一切の衆生が本来、菩薩であると明かすのが法華経の「人開会」です。
表面の姿ではなく、いわば、生命の次元で、衆生を平等に見て、統一するわけです。
その平等の生命の法理を明らかにしたのが、十界互具であり、一念三千だね。
人記品でも、阿難の「多聞第一」は、声聞としての実践ではなく、菩薩としての「本願」に基づくものだと明かされます。
仏の侍者として法を多く聞き、伝持することによって、人々を成仏に導いていけるからです。
羅睺羅の「蜜行第一」も同じです。羅睺羅が釈尊の子として生まれ、釈尊が悟りを得てから弟子となったのは、決して声聞になったのではなく、一心に成仏を求めるための蜜行であると説かれます。
つまり、人知れぬ菩薩行だということです。学・無学の声聞たちも同様です。
このように、「すべての声聞は本来、菩薩である」と開いているのが五百弟子品と人記品です。この両品は、声聞開会をテーマとしていると見ることができる。
もちろん、「本来菩薩である」とか「成仏が確定した」というのは、迹門の立場からの見方です。本門(文底)の立場では、「我心本来の仏なり」なのです。
迹門は、菩薩行を実践して仏に成るという従因至果(因から果へ、九界から仏界へ)の立場をとります。
これに対して、本門では、久遠の仏が菩薩行を実践するという従果向因(果から因へ、仏界から九界へ)の立場をとる。この立場から言えば、菩薩の心とは本当は仏の心にほかならない。
また「深心の本願」を思い出すというのは、「久遠の下種」に立ち戻るということです。
つまり、仏に成ろうと一生懸命、努力してきたと思ったが(従因至果)、法華経の山に登って見れば、一気に視界が開けて、宇宙の大パノラマが見えてきた。
そこでは、本有常住の久遠の仏が休みなく十界の衆生を導いて、菩薩行をしておられる(従果向因)。
その振る舞いは、久遠から三世にわたって不断に続き、変わることがない。
そして自分自身を見ると、久遠の凡夫として、仏と師弟不二である。師弟一体で広宣流布へ、菩薩行をしている。
そういう生命の深き実相を、法華経の会座の衆生に示すのが「本門」です。この「本門」ついては、いずれくわしく学んで行きましょう。
【法華経】五百弟子授記品(第八章)授学無学人記品(第九章)4