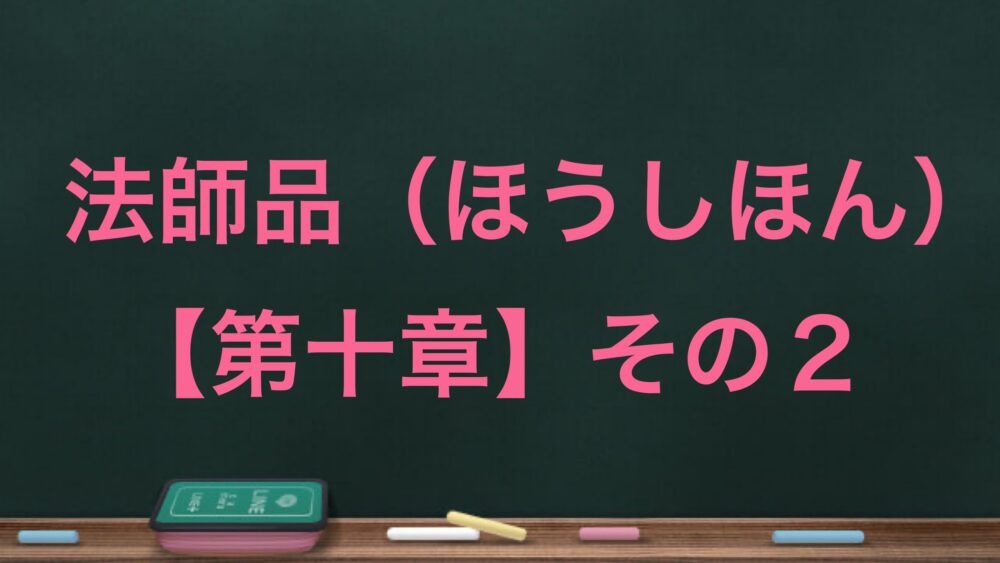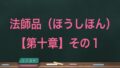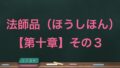法師品(第十章)その2【法華経】
法華経は「滅後のため」
法華経と共に
さっそくですが、前回の続きから始めます。
ある意味で、これまでには助走にすぎなかった。法師品から、いよいよ「釈尊の遺言」である法華経のハイライト部分が始まります。
この法師品からの展開は、前章まで大きく異なっています。と言うのは、ここから釈尊は、自分が亡くなった後(滅後)のことを、説き始めるからです。
滅後の焦点は、末法にある。何が正義で何が間違っているのか、分からなくなった時代に、人はどう生きるべきかという問題です。
このブログ(法華経)の初めに、現代を「哲学不在の時代」と位置づけましたが、それでは具体的にだれが、軌道の見えない「闇の時代」に光を灯すのか。
法師品では、その「人」を具体的に説いています。「法師」とは、現代的には「精神的指導者」と言えます。
この品の趣旨から言えば、法師という言葉には「法を師とする人」という意味と、「師となって法を弘める人」という二重の意味があります。
「法を師とする」のは、菩薩の「求道者」の側面です。「法を弘める師」とは、菩薩の「救済者」の側面です。
法師には、その両面がある。「求道」の面を忘れれば傲慢になるし、「救済」の面を忘れれば利己主義です。
学びつつ人を救い、人を救うことで、また学ぶのです。
「求道」即「救済」、「救済」即「求道」です。ここに、人間としての無上の軌道があります。
「人間として」です。
もはや在家・出家の区別などには意味がありません。
法師品に、法師とは「在家・出家の法華経を読誦する者」とあるように、在家・出家という区別を超えた存在です。
法師は、自ら法華経を受持・読誦するとともに、人々に向かって法華経を説きます。
法師の実践は、語りに語り、人々に法華経を聞かせることでした。
言論戦です。対話の戦いです。私たちの対話こそ、まさに法師品の心に合致しています。
釈尊の一生も、入滅のその日まで、人々に語り続けた一生でした。日蓮大聖人も、当時の日本人で、あれほど膨大な著述を残された人はいない、と言われています。
まさに、書きに書き、語りに語りぬいていかれた。
その尊きお振る舞いがあるからこそ、後世の人類は仏法を知ることができたのです。
言論戦です。
言論は、その時代はもちろん、後世をも照らしていくのです。
これまで学んだ方便品(第二章)から人記品(第九章)までの八品は、「今いる弟子たちを、どう成仏させるか」が中心テーマでした。
この説法の結果、すべての声聞の弟子たちが成仏の軌道に入りました。つまり、釈尊の直弟子の成仏を確定したのが人記品までの説法であり、その意味では「在世の衆生のため」の説法であったと言えます。
たしかに、この八品を見るかぎりでは、そのようにも見える。しかし、法華経全体から見れば、八品もじつは、「滅後の衆生のため」なのです。
八品だけではなく。法華経全体が「滅後のため」なのです。
日蓮大聖人は、迹門(前半部分)は一応、在世の声聞のために説かれていますが、一歩、深く見ると、本門(後半部分)と同様、滅後・末法の凡夫のために説かれたものだとされています。
在世は短く、滅後は長い。在世の門下は少なく、滅後の衆生は無量です。「一切の人を救いたい」という仏の大慈悲は、必然的に、自分の死後を、どうするかということが焦点となっていく。
この「仏の大慈悲」を一身に体して行動するのが法師です。「如来の使い」です。そこに、法師品以降が大切であるゆえんがあります。
大聖人は、法師品から安楽行品(第十四章)までの五品は、その前の八品で明かした「一仏乗」の法を、末法の凡夫がどのように修行すべきか、を説いていると仰せです。
御書
「方便品より人記品に至るまで八品は正には二乗作仏を明し傍には菩薩凡夫の作仏を明かす、法師・宝塔・提婆・勧持・安楽の五品は上の八品を末代の凡夫の修行す可き様を説くなり」
方便品から人記品に至るまでの八品は正意としては二乗作仏を明かし、傍意としては菩薩や凡夫の作仏を明かしている。法師品・宝塔品・提婆達多品・勧持品・安楽行品の五品は上の八品に説かれた法門を末法の凡夫が修行すべき方途を説いているのである。
「末法の凡夫」とは、大聖人であられる。総じては、大聖人に連なる門下のことです。大聖人は、御書の随所に、法師品など五品の経文を引用されている。法華経の中でも、法師品以降、滅後について説かれた個所の引用は圧倒的に多い。
それは、ここに説かれた滅後の「法華経の行者」の姿が、そのまま日蓮大聖人のお振る舞いと一致しているからです。言い換えれば、法華経を身で読まれたのは大聖人お一人であり、法華経は大聖人のために説かれたのである、という証明になっています。
そして、仏を仏にした「根源の一法」である「南無妙法蓮華経」こそが、法華経の真髄であり、末法すべての衆生を救う大法であることを教えようとされたのです。
それで、法師には仏に対するのと同じ供養をすべきであると、法師品で説いているわけが分かります。
この個所を梵本で見ると、法師について、より明確に「如来であるとみなされるべきである」「如来と等しい者である」と説かれています。
さらに、法師は、仏から派遣されて如来の仕事を行う「如来の使い」であるとも説かれています。
大聖人の御書で、しばしば引用されている重要な経文です。
また、一言でも誹謗する罪は、仏を一劫という長い間、面前で誹謗し続ける罪よりもさらに重い。逆に、仏を一劫の間、無量の偈をもって讃嘆するよりも、法師を讃嘆する功徳のほうが勝るとも説かれます。
それは、一つには、仏よりも法こそが成仏の原因であり、大切だからです。法華経は、釈尊を含めて、あらゆる仏を仏たらしめた「根源の法」を説く経典です。その「本因」の法を説くのが末法の法師なのです。
法が能生(生まれさせるもの)、仏が所生(生まれるもの)という関係です。
大聖人は、この「法」のことを「慈悲の極理」だと言われています。
「唱法華題目抄」に「一切の諸仏・菩薩は我等が慈悲の父母此の仏菩薩の衆生を教化する慈悲の極理は唯法華経にのみとどまれりとおぼしめせ〈中略〉法華経の一切経に勝れ候故は但此の事に侍り」
「慈悲の極理」具体的には「南無妙法蓮華経」の法が含まれているからこそ、法華経は一切経に勝れているのです。あらゆる人々を救える、慈悲の大法です。法師品には「法華最第一」とあります。
有名な「已今当」の経文も、そのことを示しているのです。「我が説く所の経典は無量千万億にして、已に説き、今説き、当に説くべし、而も其の中に於いて、此の法華経は最も為れ難信難解なり」
その意味では、「如来の使い」とは「慈悲の使い」ということです。法師は、法華経を受持・読・誦・解説・書写しながら(五種法師)、仏の大慈悲心を修行するわけです。
もちろん、末法は「受持即観心」で、御本尊を受け持つ修行に尽きるわけです。仏の心を生きるのです。「すべての人を救いたい」「一切の衆生を仏に」という仏の誓願に生きるのです。
それが、「受持」等の五種の修行の根っこです。形式的に法華経という経巻を所持したり、読誦したり、解説することではない。仏の心を受け、仏の慈悲を生きぬくのです。
これまでの声聞への授記と言っても、所詮は、この「仏と同じ心」を声聞たちに思い起こさせるためにあった。
そして、この心を、仏の滅後に実践する人が法師なのです。
法師品(第十章)その2【法華経】