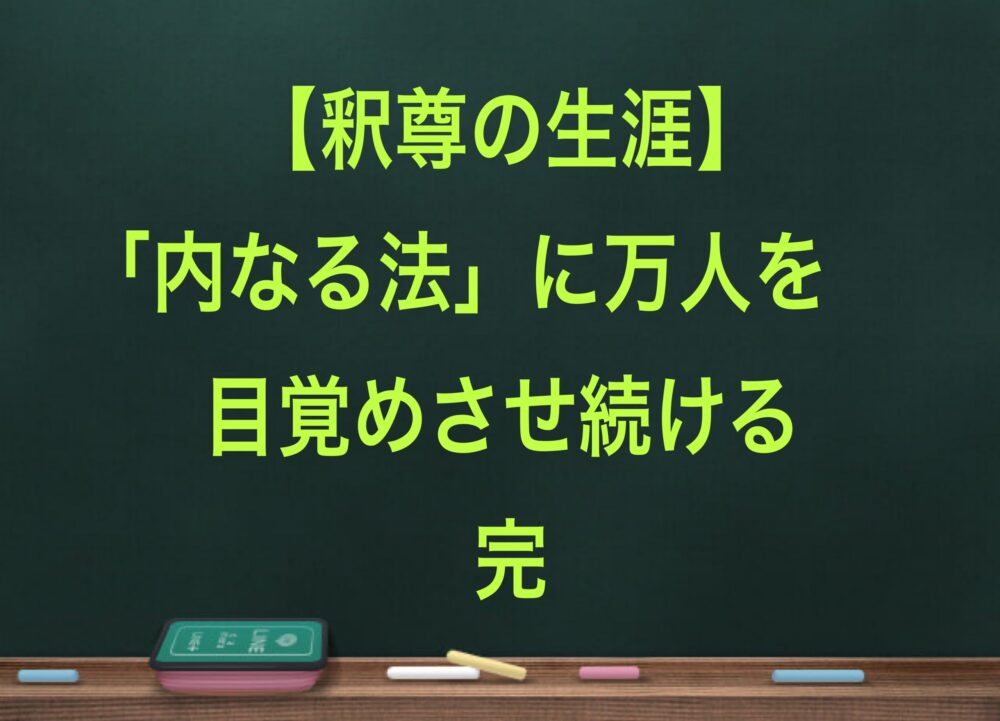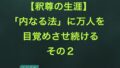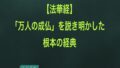【釈尊の生涯】
「内なる法」に万人を目覚めさせ続ける
完
【釈尊と法華経】
ここでは、仏法の誕生、そして、「万人の幸福」という釈尊の誓願が結晶した経典「法華経」に示される法理などを順に学んでいきます。
私たちの生命に具わる無限大の可能性を開花させるのが仏法であることを確認しましょう。
今回も、その仏法の出発点となった釈尊について学びましょう。
前回の続きを始めます。
世の常として、釈尊の名声をねたむ人々が、この頃から現れてきました。
そうした人々による、さまざまな妨害が起こりました。
釈尊が生涯のなかで経験した大難は九つあります。
これを「九横の大難」といいます。
そのうち、女性スキャンダルをデッチあげられたことが、二回ありました。
しかし、いずれも釈尊の潔白が明らかになったことは言うまでもありません。
そして、あの提婆達多との闘争もありました。
名誉や利益に流されていく弟子の提婆達多に対して、釈尊は、どこまでも求道の心を起こさせようと導き続けますが。
ある時、提婆は釈尊に、教団のリーダーとしての立場から引退するよう迫ります。
自ら、釈尊の後継者に名乗りをあげたのです。
しかし、それは私利私欲の心からでした。
その欲望の心を強く指摘された提婆は、逆恨みして、釈尊への憎みを燃え上がらせます。
提婆は、マガダ国の王子・阿闍世をそそのかし、父を幽閉(=閉じ込めること)させて王位に就かせます。
そして、阿闍世王と結託し、その権力を背景にして、釈尊を亡きものにしようと画策します。
具体的に何をやったのか。
提婆達多は、耆闍崛山(ぎしゃくっせん)から大石を落として、釈尊の命を狙いました。
また、阿闍世王は、酔わせた象を放って釈尊を踏み殺させようとしました。
これらも、九横の大難の一部です。
それでも、釈尊を倒すことができないと分かると、提婆達多は今度は、釈尊の教団の分裂を図り、一部の弟子たちを釈尊のもとから引き離します。
しかし、釈尊の高弟の舎利弗・目連の活躍で、弟子たちは教団に戻り、提婆達多の画策は失敗に終わりました。
このようにして釈尊は、人々を幸福の軌道から踏み外させる「悪」とは容赦なく戦いました。それも、釈尊の慈悲の表れです。
大難を乗り越え、弟子を育てながら、釈尊は最後まで弘教の旅を続けていくのです。
死を目前にして、釈尊は「私は、皆に、わけへだてなく、いっさいの法を説いてきた。まことの仏陀の教えというのは、奥義や秘伝などといって、握り拳のなかに、何かを隠しておくようなことはないのだ。全部、教えてあるではないか」と、悟りのすべてを説き切ったことを宣言しました。
釈尊亡きあとの時代の人々が、仏法によって人生の幸福を勝ち取っていけるようにです。
さらに釈尊は、弟子たちが「正しい教え(法)」と「自分自身」を拠り所としていくべきことを教えています。
そして「すべては過ぎ去ってゆく。怠りなく励み、修行を完成させなさい‥‥‥」との言葉を最後に、釈尊は倶尸那城(くしなじょう)の近くで八十年とされる生涯を閉じました。
釈尊の葬儀は生前の教えにしたがって、出家者は関与せず、在家の人々によって行われました。
仏教は、その誕生から「万人に開かれた宗教」でした。
釈尊は、万人にあてはまる真理、すなわち「生命の法」を万人の胸中に、いわば花開かせるために、それを阻む「悪」と戦いながら、仏法を弘め続けたのです。
仏法の原点は、釈尊が内なる法に目覚めたことです。
菩提樹の下で内面への深い探求を続けた釈尊は法(ダルマ)をありありと覚知したのです。
仏の原語は、サンスクリットの「ブッダ」です。これは「(真理に)目覚めた人」という意味です。
当時の諸宗教でも用いられたが、釈尊が登場した後、やがて専ら釈尊を指して用いられるようになりました。
それと同時に、「ブッダ」の原語には、「開花する」という意味合いがある。
人格の薫り高く爛漫と花を咲かせ、福徳の果実をたわわに実らせる人が、ブッダです。「法」の功徳を体現し、福徳あふれる人格として輝く人です。
釈尊の生涯に思いを馳せると、新たな勇気がわいてきます。
法難に次ぐ法難であった。試練に次ぐ試練であり、激動に次ぐ激動であった。そのなかで釈尊は、命ある限り法を説き、語りに語って、波瀾の大生涯の幕を閉じた。
その大闘争があってこそ、仏教は東洋に広まったのでしょう。
【釈尊の生涯】
「内なる法」に万人を目覚めさせ続ける
完